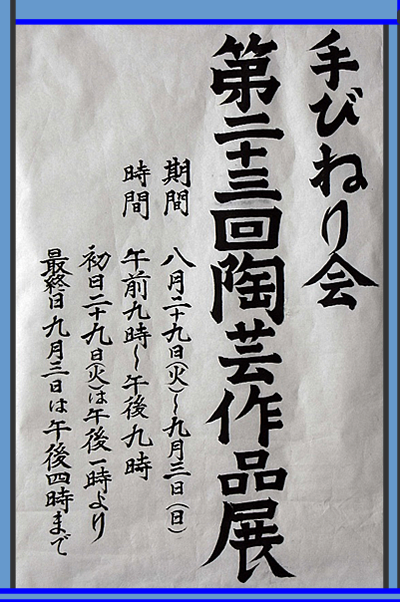質感、温もりある作風
ファブリックアートの魅力
――色や形、大きさも自由な布地のキャンバスに、つるっとしたり、ざらっとしたりの布と糸の質感で風景から静物、人物を絵のように描くファブリックアート。「60の手習い」で始めた東京都三鷹市の山浦倫子(みちこ)さん(77)が8月3日、近くの公会堂にたくさんの作品を持ち込んだ。

■写真上:畳に「お能」などの大作が並んだ和室
長年にわたって作り続け、自宅にある作品整理のためだ。1階の和室二間がギャラリーとなり、畳の上や四方の壁が展示スペースになった。

■写真上:ピカソのゲルニカを模したお気に入りの作品を紹介する山浦倫子さん
畳2畳はあろうかという「お能」は5人がステージで舞い、演者の髪に毛糸が使われて立体感がある。歌舞伎の演目「白波五人男」も畳1畳もある「大作」だ。

■写真上:「白波五人男」(左)、「御神乗太鼓」
会場にはA3判の大きさに花を描いた初期のものから留袖を使った円熟期のものがずらりと並んだ。近所の知り合いが続々と見学に来て「すごいじゃん」「上手いものだ」と感心した。
 山浦さんは23歳の時、出産を機に区役所を退職し、専業主婦になって二女一男の母になった。子どもに手がかからなくなってからパートの仕事などを続けた。保育助手を最後に60歳の時に仕事から離れ、ファブリックアートを始めた。
山浦さんは23歳の時、出産を機に区役所を退職し、専業主婦になって二女一男の母になった。子どもに手がかからなくなってからパートの仕事などを続けた。保育助手を最後に60歳の時に仕事から離れ、ファブリックアートを始めた。
■写真:初期の作品「タイサンボク」
きっかけは「思い出の布で作品づくりをしませんか」という新聞記事。ファブリックアートの考案者で、アート教室を主宰する作家三浦園子さん(東京都在住)の紹介記事だった。
「亡くなった母の着物がたくさん残っていた。その記事を読んで使うことを思い立った」が動機だった。

■写真上:「踊り」
三浦さんの教室に通った。作品はまず下絵を描き、パーツごとの型紙を作り、それに合わせて布を切る。番号をつけて目印にし、両面接着シートで布キャンバスに貼り付け、アイロンがけをする。最後にミシンを掛けて固定させる。
「亡くなった母は人の着物を縫うほど器用だったけど、私は母の回りで飛び跳ねているだけで雑巾一つ縫えなかった」と山浦さん。

■写真上:留めそでを使った「風の盆」(左)、「雪道を歩く女」
業務用ミシンの使い方を基礎から1、2年みっちり習ってからの作品づくりになった。次の課題は何を描くか。美術系の本、雑誌をめくって好きな絵柄を探したり、歌舞伎、能の場面を考えたり。
描くものが決まると次は色集めの素材探し。「基本的に着物を素材にした作品づくりをしている。でも、着物ばかりだと地味な色になってしまうので、洋服の派手目な色をミックスして彩を調整している」
ほとんどは着物や古着の素材の色目、質感を生かすが「蚊帳の中の遊女」はガーゼを染めて蚊帳に見立てたり「冬の八甲田」は降り積もる雪を素材の違う白い布を何枚も重ねて表現したりした。

■写真上:「蚊帳の中の遊女」

■写真上:「朝」(左)、「雪の八甲田」
「江戸の賑わい」は72人の男女が描かれ、一人ひとりの衣装を選び、表情を絵筆で描くなどした労作だ。

■写真上:「江戸の賑わい」
習い始めて5年後、地元の三鷹市で開催する指導者三浦さんの作品展に教室の仲間とともに参加するようになった。
「途中、なんか飽きちゃってやめようかな、って思ったことがある。でも、先生が熱心だったし、教室で出来たお友達との縁もあって続けられた」
同公会堂に持ってきたのは作品の一部。山浦さんの自宅では玄関で「花の衝立」が出迎え、2階和室の押し入れにひょうたんや「光源氏」が描かれている。室内には色とりどりの3連の花ののれんも飾られていた。

■写真上:自宅玄関にある「花の衝立」(上)、和室の押し入れの「光源氏」
公会堂に並んだ大作などの作品群もすごいが、山浦さんの自宅では手作りの温かみがあるファブリックアートが日常生活に溶け込んでいた。

■写真上:押し入れにあしらった「ひょうたん」
1980年頃から山形県出身で東京デザインアカデミー卒業の三浦園子さん(東京都)が取り組んで考案。 個人教室で希望者を指導。教室の生徒らとともに個展を開催している。
(文・写真 佐々木和彦)