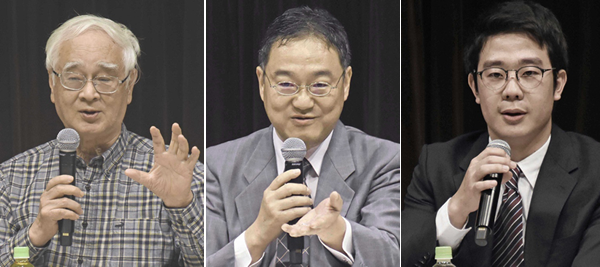我孫子ゆかりの式場隆三郎展
医療・文化・芸術の足跡をたどる

■写真上:展示室入り口に張り出されているポスター
1920(大正9)年秋、我孫子の手賀沼湖畔に住む思想家柳宗悦(1889~1961)を新潟の医学生が訪れた。民藝(民衆的工藝)運動などの手ほどきを受けに来た若き日の式場隆三郎(1898~1965)だった。
手賀沼湖畔の我孫子市白樺文学館で、柳に師事し、精神科医にして文化・芸術分野で活動した式場の足跡をたどる「式場隆三郎展―見えない世界の美しさに心をよせて」(前期)が開かれた。柳の妻兼子愛用のピアノがある1階、らせん階段を昇った2階の各展示室で写真や書籍、パネルを使った式場の活動が紹介された。

■写真上:団体客でにぎわう2階の大展示室
新潟県五泉町(現・五泉市)生まれの式場は幼い頃から文学に興味を持った。進学した旧制村松中学校(現・新潟県立村松高校)、新潟医学専門学校(現・新潟大学医学部)で文芸雑誌を次々と編集した。

■写真上:白樺文学館入り口にある佐治正大さんの彫刻「自帰依」(じきえ)(左)、柳宗悦の妻兼子のピアノがある1階中展示室から企画展が始まる
柳や武者小路実篤(1885~1976)らの雑誌「白樺」の影響を受け、のちに「民藝のプロデューサー」を自認した同級生の耳鼻咽喉科医吉田璋也(1898~1972)らとともに文化団体「アダム社」や文芸雑誌「アダム」をつくった。

■写真上:展示品を説明する式場病院学術研究部の山田真理子さん
武者小路の「新しき村」に共感し「新しき村新潟支部」を設立し、1920(大正9)年9月、武者小路を新潟に招いて講演会を開いた。この縁もあって式場は吉田らとともに我孫子の柳を訪ねたのだ。
柳が唱える民藝は庶民が生み出す生活に忠実な工芸品で、利益ではなく使う人の心、助け合って共に生きる人を思う品々だ。式場も「正しい工芸は人間の心から生まれたもの。それに触れるには心の眼を開かねばならない」と語る。
日常生活で家具や器の焼き物など各地の民藝に囲まれていた式場は「月刊民藝」(1941年9月号)にこんな記述を残している。「患者に薬を飲ませたり、注射をしたりも仕事の一部だが、複雑な精神生活はそういうものでは救われない。生活全般の建て直しをしなければならぬ。民藝運動が人間を健康にする」

■写真上:1939(昭和14)年に完成した式場隆三郎邸。建築には柳宗悦、濱田庄司ら民藝仲間がかかわった(左)、焼き物などの民藝品であふれる式場邸の居間
柳らの民藝運動とともに「微笑む仏像」の「木喰仏」(もくじきぶつ)を制作した江戸時代後期の僧侶・木喰上人(1817~1810)の研究にも参加し「木喰仏」から己の生き方も見出した。
「白樺」を読んでオランダの画家ゴッホ(1853~1890)に興味を持った。1929(昭和4)年、31歳の時に渡欧し、ゴッホ関係者に会ったり、資料を集めたり。3年後に「ファン・ホッホの生涯と精神病」(上下巻)を上梓するなど、ゴッホ関連の著作や訳本を数多く世に送り出した。

■写真上:式場がデザインしたゴッホ浴衣「自画像」(左)、自宅で民藝を愛でる式場(昭和30年代)
静岡県内の病院長を務めた後、1936(昭和11)年、柳ゆかりの我孫子周辺で土地を探し、最終的には市川市で国府台病院(現・式場病院)を開設した。同じ頃に社会福祉施設「八幡学園」の顧問医となって「放浪の画家」山下清(1922~1971)と出会う。

■写真上:式場隆三郎編「月刊民藝」(1939<昭和14>年~1946<昭和21>年)(左)、ゴッホ研究に関する著作。題字を柳宗悦、装填を型絵染の芹沢銈介が担当した
東京・浅草生まれの山下は、幼い頃の高熱の後遺症から言葉がどもるようになった。学校でからかわれたり、いじめられたりしたことから、12歳の時に「八幡学園」に移った。
式場は学園が採り入れた「ちぎり絵」(貼り絵)で頭角を現した山下の才能を高くした。陶磁器やペン画、テキスタイルデザインへの取り組みも指導し、山下作品を雑誌や画集で取り上げ、全国展覧会なども企画して、広く世間に紹介した。
式場の盟友、吉田は「彼(式場)の生涯で一番よかったのは、山下清を発見し、彼とその絵を世に紹介したことだ」と語っている。

■写真上:式場が才能を見出した山下清の作品コーナー(左)、絵皿は式場の発案で取り組んだという
民藝運動、木喰仏やゴッホ研究、そして山下清のサポート……。多岐な活動を展開した式場展を企画・監修した式場病院学術研究部の山田真理子さんは「ゴッホも山下清も式場がリスペクトと愛を寄せた人物。解説書を出し、展覧会を開くなどで私たちの手の届くものにすることで彼らの心を共有しようとしたのでしょう」と解説。
「式場は人を大事にし、のびのびと生活や仕事を楽しんだ人。『式場先生~』と皆から慕われ、一言でいうと『民藝品』のような人でしょうか」と付け加えた。
10月17日からは日本点字図書館支援など盲人福祉への情熱を中心にした後期展示が始まる。
(文・写真 佐々木和彦)


 ギャラリーの三方の壁際には銅板をたたいたり、しぼったりして形作った40点が置かれた。高さ1㍍を超える大物もある。「今回は照明を工夫した」(企画スタッフ)とあって、スポットライトを浴びたオブジェの影が壁に映る。
ギャラリーの三方の壁際には銅板をたたいたり、しぼったりして形作った40点が置かれた。高さ1㍍を超える大物もある。「今回は照明を工夫した」(企画スタッフ)とあって、スポットライトを浴びたオブジェの影が壁に映る。